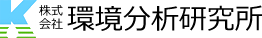湖沼の水質の指標
周囲の環境と、そこに暮らす生物や植物には、密接なかかわりがあります。ここでは、環境の変化の指標となる植物や動物、自然現象を紹介します。
湖や沼は、河川とは異なり、水の流れがない「止水域」であるため、酸素が水に溶け込むのは、ほぼ水面からに限られます。そのため、水がきれいか(透き通っているか)どうかによって、溶け込んでいる酸素の量、つまり生物が消費できる酸素の量が異なります。溶け込んでいる酸素の量(酸素溶存量)によって、そこに棲める生物の種類が異なることから、湖底の泥にどんな生物がいるかということが、湖沼の水質を表す指標になります。
汚れ(汚濁)が少なく、年間を通じて湖底まで酸素が存在する湖沼には、イトミミズやユスリカ(幼虫)類が生息します。汚れが多い湖沼では、植物がよく繁る夏の間は、水面から取り入れられる酸素の量が少なくなり、湖底の酸素が不足するようになるため、オオユスリカ(幼虫)等が多くなります。さらに汚れが多い湖沼では、湖底にほとんど酸素がなくなる期間がしばらく続くようになるため、フサカ(幼虫)が多くを占めます。フサカは、体内に空気をためる袋を持つため、酸素がない状態でも生存可能だといわれています。


最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
●戸建住宅などの水道水水質検査 詳しくはこちらから
●共同住宅や店舗、学校などの建築物飲料水検査や食品営業水質検査 詳しくはこちらから
●井戸水の飲用井戸水検査 詳しくはこちらから