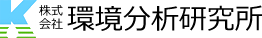温泉(共同浴場について)
温泉あれこれ(その4)…共同浴場を楽しもう
地元の人が管理する共同浴場
昔ながらの温泉地には、「共同浴場」が多く見られます。共同浴場とは、温泉を利用して地元の人々が管理する公衆浴場のこと。「共同湯」と呼ばれることもあり、もともとは地域住民や湯治に訪れる人のためのお風呂だったようです。
低料金、あるいは無料で利用できる浴場が多く、現在は観光の一環として誰でも利用できる共同浴場も増えてきました。中には複数の共同浴場が点在する温泉地もあり、「外湯めぐり」という、いわゆる温泉のハシゴを楽しむ観光スタイルも人気を呼んでいます。
また、プチ共同浴場的な存在として、短時間で気軽に温泉気分に浸れる“足湯”を設置している温泉地も少なくありません。JR常磐線湯本駅には、なんと下りホーム内に足湯が。電車を待つ時間が、ちょっと特別なものに感じられそうです。
ルールやマナーを守って楽しもう
温泉地に赴くのであれば、旅館の内湯を楽しみつつ、地域ならではの共同浴場も楽しんでみてはいかがでしょう。
ただしそれぞれ独自のルールや特徴があるので、事前によく確認を。地元住民専用の共同浴場や、一般利用の曜日が限定されている共同浴場もありますし、中には男女別の脱衣所がないところも。また飯坂温泉のように、9つの共同浴場の平均温度が44~46℃とかなり熱いお風呂もあります。
でも例えば、地元の人にそんな熱いお風呂の入り方を教えてもらったり、近隣の美味しいお店を尋ねたりするのも共同浴場ならではの楽しいコミュニケーションになりそうです。もちろん、多くの人が利用することを心に留め、マナーを守って楽しみたいものですね。

最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
●食品、土壌、水などに含まれる放射能濃度を測定する放射能検査
詳しくはこちらから