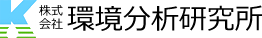職人の手仕事~伝統工芸
職人の手仕事~伝統工芸(その2)…絵のぼり
端午の節句の大空にはためく豪快な「絵のぼり」
5月5日の端午の節句に、大空に向かって掲げられる「絵のぼり」。力強さを感じさせる図柄や鮮やかな色彩が目を引きます。
絵のぼりは7世紀に中国から伝わりました。古くは村の象徴として、戦国時代には戦の陣や敵味方を識別するシンボルとして用いられたと言われています。やがて平和な江戸時代に入ると、男の子の誕生を祝い、健やかな成長を願って飾られるようになりました。そのため、「五月のぼり」「節句のぼり」などとも呼ばれます。
また中国の魔除けの神様「鍾馗(しょうき)」を始め、牛若丸と弁慶や、川中島の戦いの龍虎といった武将の絵柄が好まれていることから、「武者絵のぼり」とも呼ばれています。立身出世を表す中国の故事「登竜門」にちなんだ、鯉の滝登りの図柄も人気。ちなみに良く知られている鯉のぼりは、絵のぼりから派生したもの。歴史としては、絵のぼりの方が先なのですね。
松平定信の御用絵師から始まった「須賀川絵のぼり」
福島県では、須賀川といわきで絵のぼりが古くから作られており、いずれも1997年に県の伝統的工芸品に指定されています。
「須賀川絵のぼり」の始まりは、江戸時代。白河藩主・松平定信の御用絵師として活躍していた亜欧堂田善(あおうどうでんぜん)が、晩年になって故郷・須賀川に戻り、町絵師として様々な絵を描いたことに端を発しています。中でも注目されたのが、布地に描かれた鍾馗でした。それが端午の節句の際、人々によって飾られるようになり、やがて男児誕生のお祝いと無病息災を願うのぼり旗になっていったのです。
その後、亜欧堂田善の門弟から、須賀川で呉服屋を営んでいた吉野屋の初代・大野松岳に技術が継承され、やがて須賀川の工芸品として知られるようになりました。昭和30年代には市内に数軒の絵のぼり制作工房が存在していましたが、現在は吉野屋一軒のみ。六代目が手描き染めの伝統を守りながら、室内絵のぼりなど独自の作品を生み出し、海外でも高く評価されています。
●須賀川絵のぼり 吉野屋
https://enobori.com/
藩主の御触れで文化が広がった「いわき絵のぼり」
「いわき絵のぼり」の詳しい歴史は分かっていませんが、17世紀の磐城平藩主・内藤義概(ないとうよしむね)が「端午の節句に絵のぼりを飾って町を彩るように」との御触れを発布したとされており、これをきっかけに多くの絵師が育ったと考えられます。また江戸時代から明治初期のいわきの風習を記した「磐城誌料歳時民俗記」に絵のぼりに関する記述があり、当時は裕福な家で数10本~100本以上もの絵のぼりを掲げていたのだとか。
現在、市内には数軒の制作工房があり、昔ながらの手描き顔料染めでその伝統を継承しつつ、時代のニーズに応える制作にも意欲的に取り組んでいます。またいわきでは、勿来の関とかかわりのある八幡太郎(源義家)の図柄が好まれていることも特徴の一つ。八幡太郎のような、文武両道の子に育ってほしいという願いが込められています。
●いわき絵のぼり
◇高橋工房
https://takahashikoubou.jp/
◇いわき絵のぼり吉田
https://musyae.com/index.html

最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
● 食品、土壌、水などに含まれる放射能濃度を測定する放射能検査
詳しくはこちらから