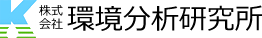職人の手仕事~伝統工芸
職人の手仕事~伝統工芸(その11)…白河だるま
見るからに福々しい白河藩奨励の縁起物
眉毛、びん、ひげ、あごに「鶴亀松竹梅」の縁起物が描かれた福々しさと、東北系のだるまに比べて丸みがあり穏やかな顔が特徴の「白河だるま」。関東系だるまに属するとも言われていますが、大型の白河だるまの中には東北系だるまによく見られる宝船が描かれているものもあり、関東系だるまの北限で東北系だるまの意匠が取り入れられた、非常に特徴的な伝統工芸品と言えます。
白河だるまの起源は、今から約300年前。江戸時代に白河藩主・松平定信が、お抱え絵師の谷文晁(たに ぶんちょう)にだるまの原案を描かせたことに始まると言われており、産業振興政策の一つとして奨励されました。1997年には福島県伝統工芸品に指定されています。
かつては目が最初から入っているだるまが販売されていましたが、昭和に入った頃から「目なしだるま」の販売が中心になっていったのだとか。まずは願い事を託してだるまの左目(向かって右側)に目を入れ、成就したらもう片方に目を入れます。そして翌年、一回り大きなだるまを買い増やすことが風習となっており、末広がりの縁起物としても知られています。
現在、白河だるまを製造しているのは「佐川だるま製造所」と「白河だるま総本舗」の2軒。それぞれ手作業で丁寧に作っており、それゆえ一つ一つの表情に唯一の個性が宿っています。またスタンダードなだるまだけでなく、最近はユニークな変わりだるまも続々登場。インテリアやプレゼントとしても重宝されるようになりました。
約500軒の露店が並ぶ「白河だるま市」
毎年2月11日、白河駅前を中心に目抜き通り約1.5kmで「白河だるま市」が開催されます。白河ではかつて、奥州街道沿いの天神町・中町・本町・横町・田町の「通り五町」で市が開催されており、特に中町の「市神様」が盛大でにぎわっていました。市神様では最初は正月飾りや花飾りなどが売られていましたが、後に販売物の中心がだるまとなり、「だるま市」と称されるようになったのだそうです。
今年も2月11日(火・祝)に白河だるま市を開催。白河だるまを始め、縁起物や飲食物など約500軒の露店が立ち並び、約15万人もの人出でにぎわいます。身動きも取れないほど混み合う通りを歩きながら、自分だけのだるまを見つけてみてはいかがでしょう。
また同日、天神町と本町では「どんど焼き」と呼ばれる火祭りも開催。その年の正月飾りや旧年のだるまの供養もしてもらえます。
◆白河だるまの工房◆※それぞれ絵付け体験などもおこなっています。
佐川だるま製造所
https://www.sagawa-daruma.com/
白河だるま総本舗
http://www.shirakawadaruma.com/

最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
● 食品、土壌、水などに含まれる放射能濃度を測定する放射能検査
詳しくはこちらから