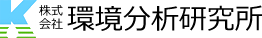やませ
風の名前(その2)……「やませ」
春から夏(6月〜8月)に、主に東北地方の太平洋側で吹く、冷たく湿った東よりの風は、「やませ」と呼ばれます。気象用語としての「やませ」は「山を越えて吹いてくるフェーン現象の性質を有する乾燥した風」のことですが、東北地方太平洋側に吹く「やませ」は、それとは別の物です。
やませが発生するのは、上空約1500mまでの低層の大気の温度が低く、1500mよりも高いところの大気が高温の状態の時です。寒流の親潮の上を通って海から吹き渡ってくる冷たい空気が、奥羽山脈を越えることができず、陸地に滞留するため、低温傾向が継続します。下層雲や霧が出たり、小雨や霧雨になることもあります。
稲の出穂・開花時期に当たる夏の盛りに、やませが長く吹き付けると、日照時間の減少や気温低下が起き、水稲を中心に収量が激減して「冷害」となります。福島県の浜通り北部などの稲作地帯は、岩手県の北上盆地、宮城県の仙台平野と並んで、やませの影響を最も受けやすい地域といわれています。

最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
●食品に付着している細菌の食品細菌検査 詳しくはこちらから
●調理器具などに付着している細菌の拭き取り検査 詳しくはこちらから
●室内浮遊の細菌の落下細菌検査 詳しくはこちらから