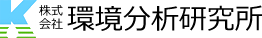秋風
風の名前(その6)……「秋風」
「秋風」は、その名の通り、秋になって吹く風です。季節の訪れを感じさせるものとして、春には「霞」「花」、夏には「ほととぎす」などが歌に詠まれますが、秋は「風」がそれにあたります。万葉集には、「朝風」や「春風」など、風を詠んだ歌がたくさんありますが、最も多く詠まれているのは「秋風」です。
福島の歌枕を詠んだものでは、後拾遺和歌集第九巻に収録の能因法師の歌がよく知られています。
都をば霞とともに立ちしかど秋風ぞ吹く白河の関
(京の都を春霞の立つ時季に出発したが、白河の関に到着した頃には、秋風が吹いていた――陸奥は都から遠いものだ)
白河の関は、この歌によって歌枕として注目され、「陸奥(みちのく)」(東北地方)への入り口の象徴となりました。白河の関そのものは、その後廃止され、江戸時代頃にはその位置もわからなくなっていましたが、1960年代の調査で、白河市旗宿がその遺構ではないかと推定されて、国の史跡に指定されました。

最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
●食品、土壌、水などに含まれる放射能濃度を測定する放射能検査 詳しくはこちらから