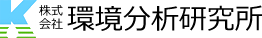河川の水質の指標
周囲の環境と、そこに暮らす生物や植物には、密接なかかわりがあります。ここでは、環境の変化の指標となる植物や動物、自然現象を紹介します。
川の中には、魚や水生昆虫、貝やサワガニの仲間、ミミズやヒルの仲間などさまざまな生きものが棲んでいます。これらを総称して水生生物といいます。水生生物は、生息できる水質(水のきれいさの程度)が、種類によって異なります。そこで、どのような生物が棲んでいるかを調べることによって、その地点の水質が判断できます。
環境省が行う全国水生生物調査では、29種類の水生生物を選び、どの生物が多く見られたかを調べることで、川の水のよごれの程度を判定しています。判定に使う生物を「指標生物」といい、この調査では、水質を「水質階級I」から「水質階級IV」までに分け、各階級ごとに指標生物が決められています。
| 水質階級 | 種類数 | 指標生物 |
| 水質階級I (きれいな水) |
10種類 | アミカ類、ナミウズムシ、カワゲラ類、サワガニ、ナガレトビケラ類、ヒラタカゲロウ類、ブユ類、ヘビトンボ、ヤマトビケラ類、ヨコエビ類 |
| 水質階級II (ややきれいな水) |
8種類 | イシマキガイ、オオシマトビケラ、カワニナ類、ゲンジボタル、コオニヤンマ、コガタシマトビケラ類、ヒラタドロムシ類、ヤマトシジミ |
| 水質階級III (きたない水) |
6種類 | イソコツブムシ類、タニシ類、ニホンドロソコエビ、シマイシビル、ミズカマキリ、ミズムシ |
| 水質階級IV (とてもきたない水) |
5種類 | アメリカザリガニ、エラミミズ、サカマキガイ、ユスリカ類、チョウバエ類 |


最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
●戸建住宅などの水道水水質検査 詳しくはこちらから
●共同住宅や店舗、学校などの建築物飲料水検査や食品営業水質検査 詳しくはこちらから
●井戸水の飲用井戸水検査 詳しくはこちらから